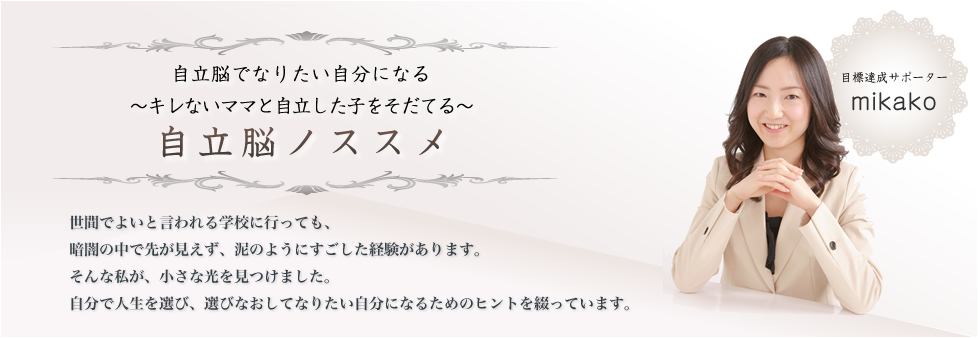本読みまえうしろ。
- 2012年10月30日 |
- └本の読み方 |

お立ち寄りくださりありがとうございます
先日は mikanta流覚える必要のある本の読み方
mikanta流覚える必要のある本の読み方 をお伝えしましたが、
をお伝えしましたが、
今回は、自己啓発やビジネス本その他諸々の本読みのお話です。
以前、前と後ろとキーワード
そしてその隙間を埋める
と書きました。
なんのこっちゃー
だと思うので、ちょこっとだけ具体例で書いてみようと思います。
まず、
目次を熟読(笑)
これで、本の構成を把握します。
次に、「はじめに」を読むと、
この本を通して何を伝えたいのかがわかります。
その次は、「おわりに」へ飛びます
ここで、結局、どんな話だったのかがだいたいわかります。
そこからようやく中身に入るわけですが、
私の場合、後ろからが多いです(笑)
なんでだろー?と考えてみたのですが、
結論。
右利きだから
右手で、ページをぜーんぶつかんで、親指でぱらぱらさせるのがちょうどよいようです。
さらに、後ろから読むメリットはほかにもあって、
各章の最終ページに、まとめらしきものがのっていることがあります。
そこから読むと、各章の概要をを把握してから中身に入ることができるのですねー
…と、ここまで書いて、
どんだけ全体像を把握したい人なんだろうと思いましたよ、我ながら
具の煮え具合とか気になって、ナベ奉行やりだす人みたいですね
そして、小見出しというのか、
章の中の節にあたる部分が、たいてい太字だったりするので、
そのキーワードを追う+現国答え探しをします。
どういうことかというと…
たとえば、小見出しが
 直観は潜在意識からの情報伝達だ
直観は潜在意識からの情報伝達だ
とか、
 最高の成功は自分に最も適した仕事を持つこと
最高の成功は自分に最も適した仕事を持つこと
とか、
 仕事は社会へ貢献すること
仕事は社会へ貢献すること
といったことだったら、
ふんふん とありがたく読みます。
とありがたく読みます。
でも、
 大欲をもつ
大欲をもつ
→どんな?
 奇跡的な治癒をもたらす3つのステップ
奇跡的な治癒をもたらす3つのステップ
→3つって?
 社会がつくる病気を治す方法
社会がつくる病気を治す方法
→なあに?
と、内容が一読了解でないものは、
その節で説明している文や単語をピンポイントで探す。
これが現国答え探しです
そして目次を読み出してから最初のページまで戻るのに、この間約10分。
もうちょっと時間があるときは周辺も見つつもう一度後ろから。
結局、頭から丁寧に読む前に、3回くらい回し終わっているということも、時にはあります
さらに、頭から丁寧に読まなくても、もういいかな?なんてこともときにはあります(笑)
全体像を把握してから読むと、
内容をつかむのに時間がかからなくなるので、
便利なのです。
…この間、これを小説でやって、10分後、母にこんなお話だよ、と、内容を説明したら、
「私まだ最後まで読んでなかったのにー。結末言わんでよー 」と、
」と、
横にいた父からクレームをうけました
というわけで、使用法には注意が必要…なこともあります
読み方あれこれでした